コンデンサーの放電
回路の設定
電荷 Q0 が充電されているコンデンサー(静電容量 C )に抵抗器(抵抗 R )を接続して、放電が進む様子を微分方程式で考える。直観的に、最初は大きな電流が流れ徐々に弱くなると予想される。ちゃんとそうなるのか、電流の時間変化の様子を数式的に求めていこう。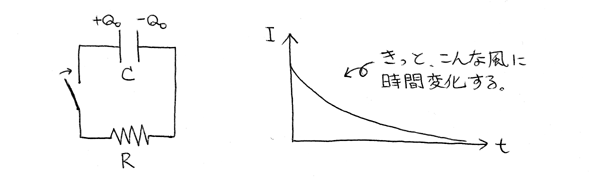
キルヒホッフの法則を微分方程式で書く
さて、キルヒホッフの法則を用いて、この回路が満たす微分方程式をたてていこう。確認すると、キルヒホッフの第1法則は電荷保存則。第2法則は回路を一周したときに電位が元に戻るということである。回路についての微分方程式をたてるときは、この両方を用いる。
さて、放電を開始した瞬間を時刻ゼロとする。時刻 t でのコンデンサーの電荷を Q(t)、回路を流れる電流を I(t) とする。電流は図のような向きをプラスとする。(逆向きをプラスとしても結論は同じになるので是非確かめてほしい)
するとキルヒホッフ第2法則より以下の式が成り立つ。
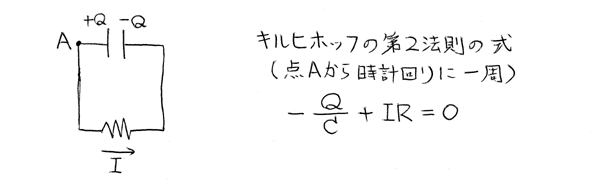
また、キルヒホッフの第1法則より電荷が保存していなければならない。つまり、コンデンサーの電荷が変化した分、電流が流れなければならない。それを式にすると下のようになる。マイナスがつくのは、プラスの向きに電流が流れたときにコンデンサーの電荷が減少するからである。
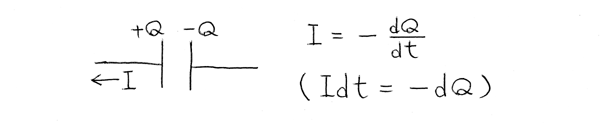
この式をキルヒホッフ第2法則の式に代入すると
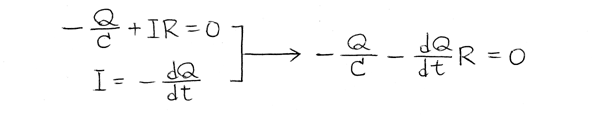
かくして、 Q についての微分方程式がたてられた。電流 I についての方程式でもよいのだが、そうすると積分方程式になってしまう。 Q についての微分方程式を解いて Q が得られれば、それを t で微分してマイナスをつけたものが電流 I なので、 Q がわかれば十分なのである。
微分方程式を解く
さて、次に Q についての微分方程式を解こう。微分方程式を解くとは、Q の値を確定するのではなく、 Q が時刻 t に対してどのような関数になっているかを確定する、ということである。どうすればそれを求めることができるのか。いま Q が満たす微分方程式は、実はもっとも単純で楽に解ける微分方程式のタイプなのである。こういうタイプの微分方程式を変数分離形という。変数分離形の微分方程式は、式の両辺に変数を分離すれば解ける。以前、高校数学のカリキュラムにあった微分方程式はこのタイプのものだ。
さて、微分方程式を下のように変形していく。この変形の目的は、 Q と t とを式の両辺に分離することである。( dQ 、 dt も含めて)。
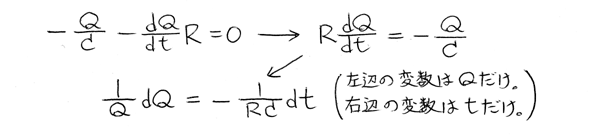
このように変数を両辺に分離すると、両辺を素朴に積分することができる。すると、 Q が t に対してどのような関数になるかを求められる。以下の式変形がそれである。
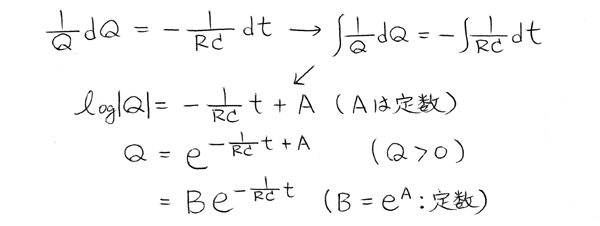
Q の中に1つ定数が出てきてしまったが、1階の微分方程式の解は、かならず1個の積分定数を含む。(このときの解を一般解という)。定数は任意であるが、現実にこの回路で起きる現象はただ一つである。よって定数を一通りに確定しなければならない。(定数が確定した解を特解という)。どのように確定するのか。その手段が初期条件である。
初期条件から特解を求める
初期条件とは、ある時刻での物理量の値のことをいう。時刻ゼロでなくてもよいのだが、いまの回路の場合、時刻ゼロのときの物理量が与えられているので文字通り初期( t = 0 )での条件を考える。時刻ゼロで、コンデンサーの電荷が Q0 だと指定されている。これが初期条件だ。よって、時刻ゼロで Q がこの値になるように定数を調整すればよい。一般解で t にゼロを代入すると、 Q = B となる。つまり、 B = Q0 だ。かくして特解が求まった。
この特解をグラフに描こう。コンデンサーの電荷がこのように減っていくことは直観的に納得できることだろう。
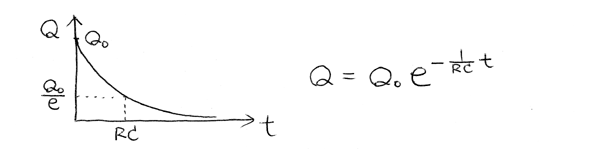
また、電荷を時間微分してマイナスをつけたものが電流であるので、電流の式とグラフは以下のようになる。これもまた、直観と合致する。
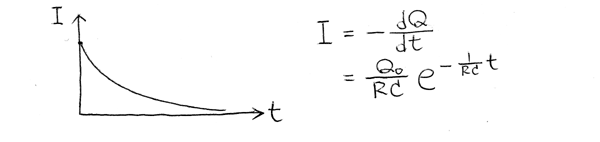
電流の大きさが R に反比例することや、電荷や電流が 1/e 倍になるのにかかる時間が抵抗 R に比例することは、直観的に理解しやすい。抵抗が大きいほど電流は流れにくいのだから。しかし、電流の大きさにコンデンサーの静電容量 C が関係するというのは意外な感じを受けるのではないか。数式を解くとこのような直観的にわかりにくい結論が得られるところも面白い。
[まとめ]
- キルヒホッフの法則を用いて、回路が満たす微分方程式をたてる。
- 微分方程式を変形して一般解を求める。
- 初期条件を考えることで一般解に含まれる定数を確定し特解を求める。
- せっかく解を求めたなら、その意味を考える。