電気振動(LC)
回路の設定
充電されているコンデンサーにコイルのみを接続すると、その後、どのような現象が起きるだろうか。高校物理でも扱うように、電気振動が起きる。その様子を、微分方程式を解く、という視点で考えてみよう。
電荷Q0を充電したコンデンサーに、自己インダクタンスLのコイルを接続して、スイッチを入れた瞬間を時刻ゼロとする。
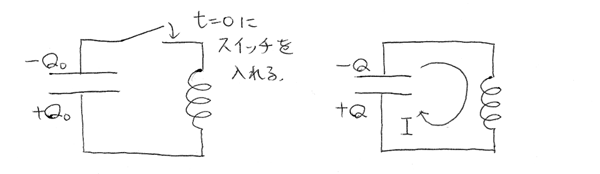
上図のようにプラスの向きの電流と、コンデンサーの極板のプラスマイナスを定義する。時刻tでの電流をI、コンデンサーの電荷をQとする。プラスの向きに電流が流れると、コンデンサーのプラス側の極板では電荷が増えるので、IとQの間には、次のような関係があるとわかる。
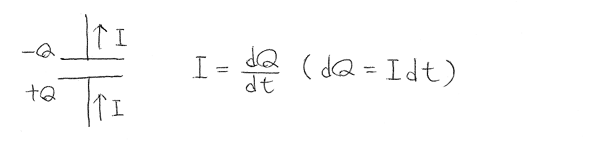
コイルは自己誘導によって、誘導起電力をつくる。そのことに気をつけてキルヒホッフ第2法則の式を立てよう。
立てたあと、さらに、上に書いたIとQの関係式を代入する。すると、以下のような形の式となる。
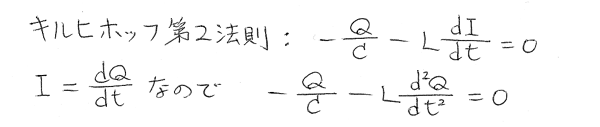
これは、力学での単振動の式にそっくりだが、それについては別な機会に書くことにしよう。
未定定数法
さて、上のキルヒホッフ第2法則から作った方程式から電荷Qが求まるはずだが、これまでと異なり2階の微分が出てきている。幸い、線形で斉次なので、解き方はそれほど難しくはない。解き方は何通りかあるが、直観的にわかりやすいものを紹介しよう。未定定数法と呼ばれる方法である。これは、解の形を予想して、定数を未定のまま微分方程式に代入し、定数を求める、というやり方である。
この2階微分方程式をみると、2階微分したものが、微分する前のものと似ていることを主張している。
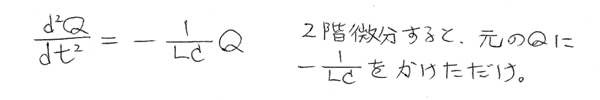
微分しても形を変えない関数として、我々はetを知っている。
そこで、この2階微分方程式の解の形を、Q=Aeλtと仮定する。ここでλが未定定数である。なぜか文字はλを使うことが多い。(Aは、ある解の定数倍も解であることを意味する積分定数)
これを微分方程式に代入すると、λについての式が得られる。このような式を特性方程式という。この式を解いてλを得る。
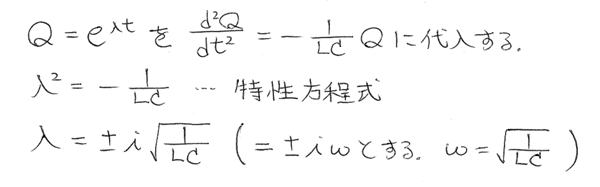
2階の微分方程式であるから、その一般解には積分定数が2つ出てくるはずである。よって、ここで得られた2つのλに対応する項の和が一般解となる。だがλとして虚数が出てしまった。しかし、コンデンサーの電荷Qが複素数になることはありえず、実数でなければならない。この暗黙の条件によって一般解の形が限定される。オイラーの式を使って整理してみよう。積分定数を工夫すれば、虚数部を消すことができる。
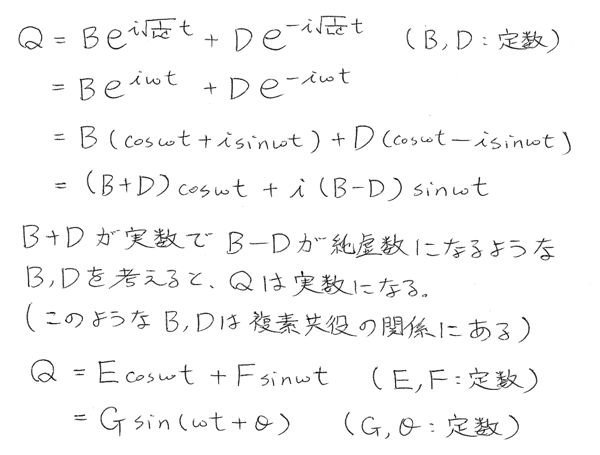
以上のように、電荷Qが満たすべき一般解が得られた。(積分定数がちゃんと2つある)。ちなみに、2階に限らず線形な斉次方程式ならば、このように特性方程式を導くことで解を得られる。
さて、一般解が得られたので、そこから初期条件を満たす特解を求めよう。初期条件は、時刻ゼロにコンデンサーの電荷がQ0で、電流がゼロ、ということである。電流は電荷Qを時刻tで微分すると得られる。
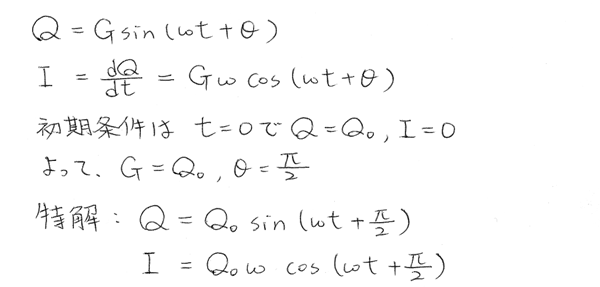
解の意味
かくして、初期条件を満たす解が得られた。次にこの解の物理的な意味を考えてみよう。電荷が周期的に変化することがわかるだろう。その周期は以下のようになる。
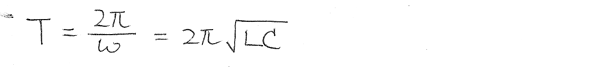
電荷と電流の時間変化の様子をグラフにしてみよう。
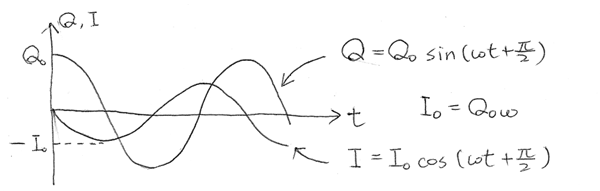
コンデンサーの電荷の大きさが最大のとき電流はゼロで、電荷がゼロのとき電流の大きさが最大となる。電流の位相が電荷に比べπ/2だけ進んでいる。
電荷がコンデンサーの極板間を、コイルを通って振動しているイメージが描けるだろうか。コンデンサーの電荷がゼロになったときに電流が止まらないのは、コイルの自己誘導のためである。
また、電流の最大値I0がωに比例するが、ωが大きいほど短い周期で電荷が振動するのだから、ωが大きいほど電流が大きくなるイメージは持ちやすいだろう。
この現象は力学の単振動とセットで理解すると良いのだが、単振動については別の機会に。
[電気振動の周期がLとCで決まる]
電気振動の周期はなぜLとCで決まるのだろう。素朴に考えてみよう。
Lが大きいとリアクタンスが大きい。Lが大きいコイルとは、自己誘導が強く、同じ電流を保とうとする「慣性」が大きい。Lが大きいコイルほど電流の変化が小さく、電流を流しはじめるのにも、流れている電流を止めるのにも時間がかかる。よって、Lが大きいほど周期は長くなる。
一方、Cが大きいほど、コンデンサーに電荷が流れ込んでもなかなか電圧が上がらない。つまりコンデンサーを充電していくときに、長い間電流が流れることになる。よってCが大きいほど周期は長くなる。
電気振動の周期はなぜLとCで決まるのだろう。素朴に考えてみよう。
Lが大きいとリアクタンスが大きい。Lが大きいコイルとは、自己誘導が強く、同じ電流を保とうとする「慣性」が大きい。Lが大きいコイルほど電流の変化が小さく、電流を流しはじめるのにも、流れている電流を止めるのにも時間がかかる。よって、Lが大きいほど周期は長くなる。
一方、Cが大きいほど、コンデンサーに電荷が流れ込んでもなかなか電圧が上がらない。つまりコンデンサーを充電していくときに、長い間電流が流れることになる。よってCが大きいほど周期は長くなる。